マーケティング検定2級の公式問題集 第5章「産業と競争の構造」を勉強したので、要約します!
「産業と競争の構造」というタイトルから、少し難しそうな気配を感じていましたが、勉強時間も短く済みそうな簡単な章でした。
中身の難易度も高くなく、「構造としての競争」と「プロセスとしての競争」という概念を理解すれば、問題なくこの章で学ぶべきことは頭に入ると思います。
マーケティング検定2級 公式問題集
第5章「産業と競争の構造」重要用語
- 構造としての競争:産業・戦略グループという枠組みによりの収益性を規定する競争
- プロセスとしての競争:知識や情報、技術などを生み出していく競争
「マーケティング検定2級は難易度高そう・・・。」
そんな風に悩んでいる方は、マーケティング検定3級についての記事も一緒にご覧ください!
マーケティング検定3級は初心者でも10~20時間勉強すれば合格できると思います。
基礎から体系的に「マーケティングとは」ということを学ぶには最適な資格です。
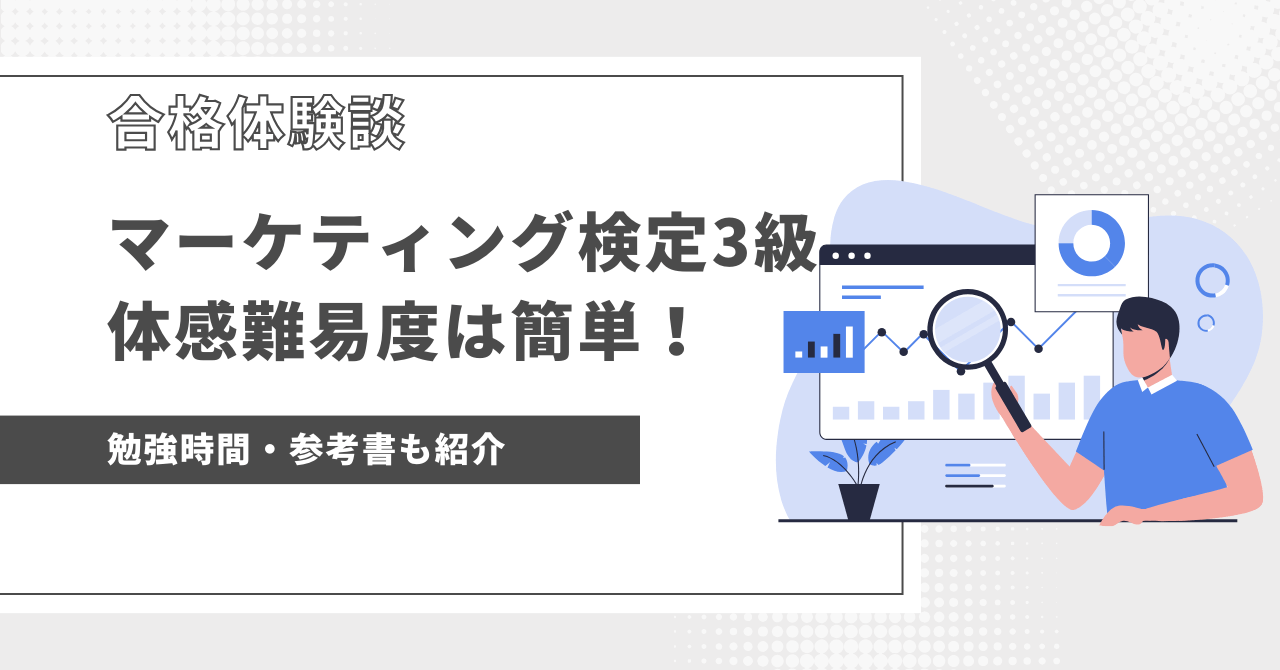
第5章:産業と競争の構造
「産業と競争の構造」という章で学ぶ内容は、2つあります。
収益性を規定するような産業の枠組みを捉えて競争とする概念。
そして、より良いものを生産していこうという試行錯誤を様々な主体が自律的に行うことで新たな知識や情報が生まれるプロセスを指した概念。
第5章では、この2つの定義と違いを理解することで、収益性に影響する要素を競走という視点から捉える内容になっています。
構造としての競争
「構造としての競争」とは、企業が属するグループにおける収益性を規定する競争のことを指します。
問題はグループをどのような単位で捉えるかによって、競合や収益性を考えるときに必要な情報の幅が変わります。
マーケティング検定2級の公式問題集では、以下の2つのグループが取り上げられています。
「構造としての競争」における代表的な枠組み
- 「技術の共通性にもとづくグループ」=産業
- 「事業構造の類似性にもとづくグループ」=戦略グループ
産業の方が広い概念です。
製品・サービスを製造したり、提供するために必要な技術。
この技術の共通性を軸にしたグループが産業となります。
事業の収益性を決める要素として、①自社の属する産業の魅力度(業界の平均的な収益性)と②その産業における自社の競争的地位が存在します。
この2つの要素が「顧客が多い、増加している」という事実と「事業の収益性が高い」ということは、必ずしも一致しない理由になります。
産業の収益性を決める要因とは?
産業の収益性を決める要因とは何か。
急に聞かれると答えるのが難しい質問ですが、しっかりと勉強しておけば原理原則として回答することは簡単です。
本章で学ぶ要因は3つ。
①:競争者の数と規模の分布
上位企業に市場シェアが集中する業界の方が収益性が高くなります。
横並びで競争しているとバリューチェーンの一部として、価格交渉力が弱くなり、結果として収益性は低くなってしまうのです。
また「最適生産規模」という用語も意識しておく必要があるでしょう。
事業規模を拡大していくと単位当たりの生産コストが下がっていくという「規模の経済性」が存在します。
しかし、一定の生産規模を超えると、その効果が効かなくなり、生産コストが上昇し始めるのです。
原材料入手や生産設備や拠点に関する土地代、マネジメント観点での管理コストなどが発生することにより、却ってコストが増加していく。
コストが増加しないで、生産規模を最大化できる規模を「最適生産規模」と言います。
最適生産規模が小さい産業は参入が容易ということになり、競争が激化。
収益性も低くなりがち。
このような考えから、産業内の企業数を決定するのに「産業全体の需要の大きさ」と「最適生産規模」の比が用いられることもあります。
②:新規参入の容易性
当然ですが、新規参入が容易な場合、その産業は収益性が低くなりやすいです。
新規参入を防ぐ、参入障壁を如何に生みだすか。
企業は自社の優位性と新規参入を妨げる術を繰り出していく必要性があります。
事業を始めるうえで、初期投資が大きい場合は新規参入は難しいです。
巨大な生産設備を建築したり、そのために土地を購入したり。
しかし、現代では製造だけを請け負う企業もあったり、3Dプリンターなど技術の発展により、スモールスタートが容易になってきている時代です。
初期投資が大きく必要な事業に仕立て上げることで参入障壁を構築するのは難しい気がしますね・・・。
他にも「特許や独自の技術」を有することや「流通チャネルの閉鎖性」を保てるように商流を押さえることも参入障壁を築くうえでの観点になります。
どちらも難しいことには変わりがないですし、時間やコストが必要になる点は変わりませんが、確かに築かれた壁を超えるのは難しそうですね。
インフラ系の事業を行う企業は「政府の規制」にも守られていることになります。
電力事業者や交通事業を想像すると分かりやすいですね。
金融業界などもFintech企業と呼ばれる新興企業が誕生してはいますが、金融庁の定める規制が厳しかったりするので、結局は従来から存在する金融機関と協力をしているケースが少なくありません。
③:差別化の程度
最後の要因は「産業に属する企業の製品・サービスの差別化がどれだけされているか」という要因です。
「差別化がされていない=どれを選んでも同じ=競争激化=価格低下=収益性低下」という構図が成り立つので、基本的な製品・サービスの性能は当然に、ブランディングの観点でも差別化がなされているというのは重要になります。
マーケティングに精通したコンサルタントを目指すのなら、差別化を意識したマーケティング施策は常に考える癖をつけましょう!
戦略グループの規定要因
戦略グループは「事業の構造に類似性が見られる企業のグループ」を指す言葉になります。
言葉だけではピンと来ないでしょうが、「垂直統合の程度(事業の深さ)×製品ラインの広がり(事業の広がり)」で戦略グループを表すことができます。
マーケティング検定2級の公式問題集に、化粧品産業の戦略グループが解説の中で記載されています。
資生堂や花王などは化粧品メーカーと直接契約を結ぶ小売店で販売しているので垂直統合は深いと言えます。
そして、高価格帯~お手軽な低価格の化粧、スキンケアやヘアケアなど製品ラインは幅広く備えています。
化粧品といっても女性向けだけではなく、男性向けの化粧品も販売していますよね。
対極の例として存在するのが、流通企業のプライベート・ブランドです。
特定のコンビニエンスストアやスーパーで、限定的な化粧品を販売していますが、限定的な化粧品を製造することに特化した化粧品メーカーが裏に存在することになるので、そのような企業は戦略グループとして「浅く・狭い」分類になるでしょう。
このように「垂直統合の程度(事業の深さ)×製品ラインの広がり(事業の広がり)」で戦略グループを定義することができます。
プロセスとしての競争
これまでは収益性を規定する「構造としての競争」についての勉強したことを振り返ってきました。
つぎは、知識や情報を生み出す「プロセスとしての競争」を学んでいきます。
第二次世界大戦前後の経済学者ハイエクは「市場の本質的な役割として、競争を通して新機軸を生み出していくことにある」と提唱しました。
当時は社会主義的に管理計画による経済活動が是とされていたが、ハイエクはこれを否定。
情報や知識を市場関係者が須らく、等しく保有して活用することを前提とした計画経済よりも、多くの個人がバラバラに競争した方が効率的だと唱えたのです。
全ての情報を管理統制することなど現代では到底不可能だと考えずとも分かることですよね。
限定的だとしても、個人や小さな組織がそれぞれで試行錯誤し、挑戦と改善を続けることが競争の本質である。
その過程で新たな知識や技術を生み出すことになる。
これが「プロセスとしての競争」という考え方になります。
「構造としての競争」は産業や戦略グループなど、収益性を規定することになりますが、「プロセスとしての競争」は試行錯誤の過程で企業の個性を創造したり、産業の枠組み自体を変更することもあります。
新たな知識や情報が生まれることで、産業の枠組み自体が(再)定義されるということです。
企業はプロセスの競争を通して、ゲームチェンジが起こっていないかを注視していないと、これまでの競争力を生み出していた価値の源泉が足かせになる可能性もあるのです。
変化の機運を感じ取ったら動き、適応していく姿勢が重要です。
競争について理解を深め、置かれた状況を俯瞰する
「産業と競争の構造」を学んだので、自分なりにまとめてみました。
マーケティングに関する知識は、施策を考えるうえでの基礎となります。
産業の枠組み自体を変化させ、自社に有利となるような駆け引きをマーケティング施策を通して行う。
とてもダイナミックで面白い観点を学ぶことができました!
まだまだマーケティング検定2級の勉強は続きます!
引き続き、勉強した内容をまとめていくので、ぜひご覧ください!
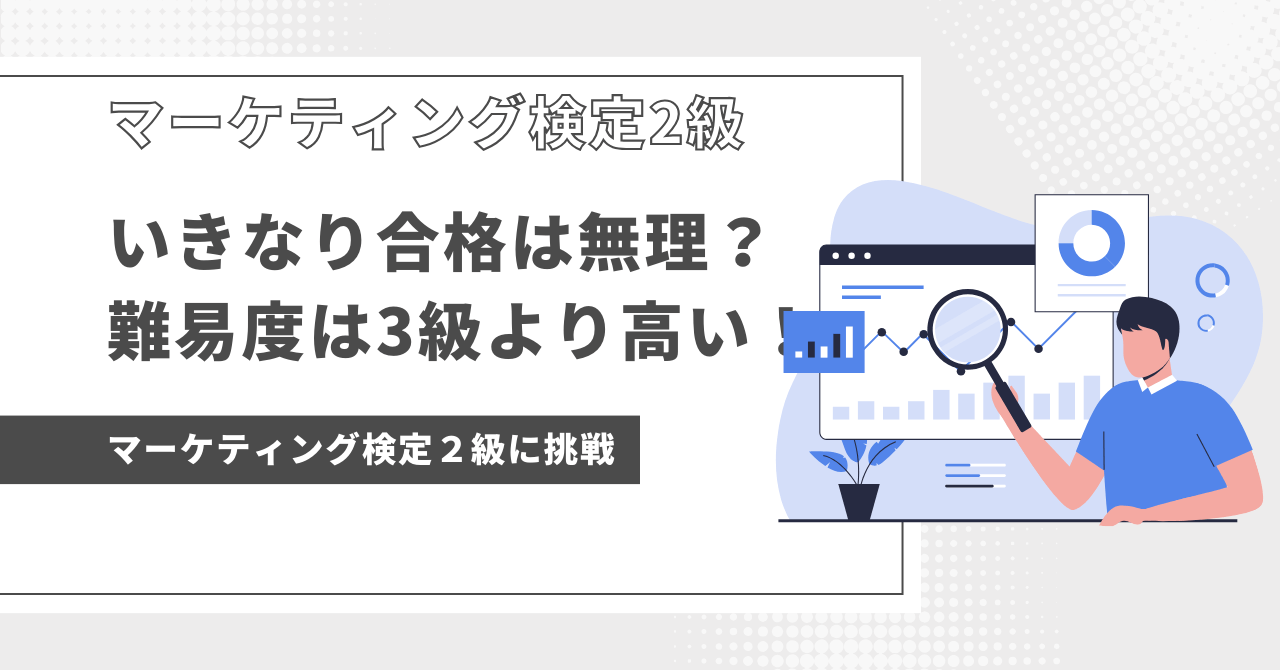
マーケティング検定2級の受験を決意された方は、ぜひ公式問題集を購入してください。
マーケティングに関する歴史的な背景やアカデミックな研究成果も解説欄にたくさん記載されているので、この2冊でしっかり学べば大学の講義は不要なのでは?と思うくらいの充実度です。
マーケティング検定2級 学習記録
マーケティング検定2級合格に向けた学習記録をまとめています。
ぜひ合格の参考にしてください!
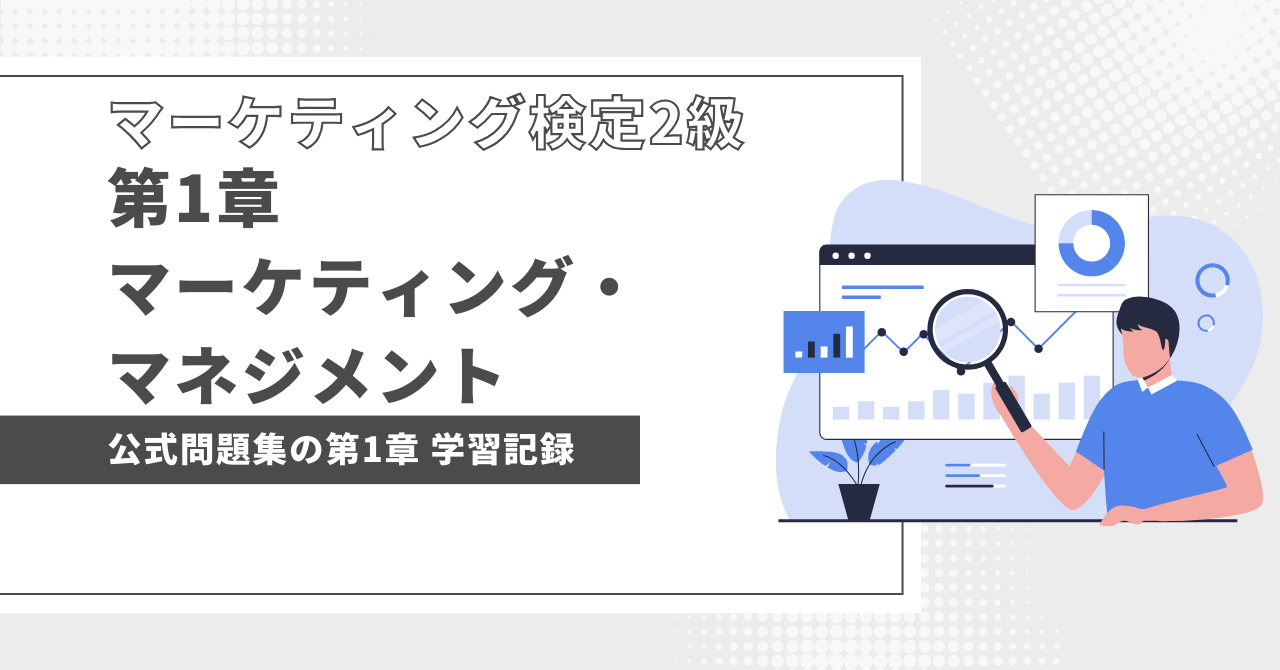
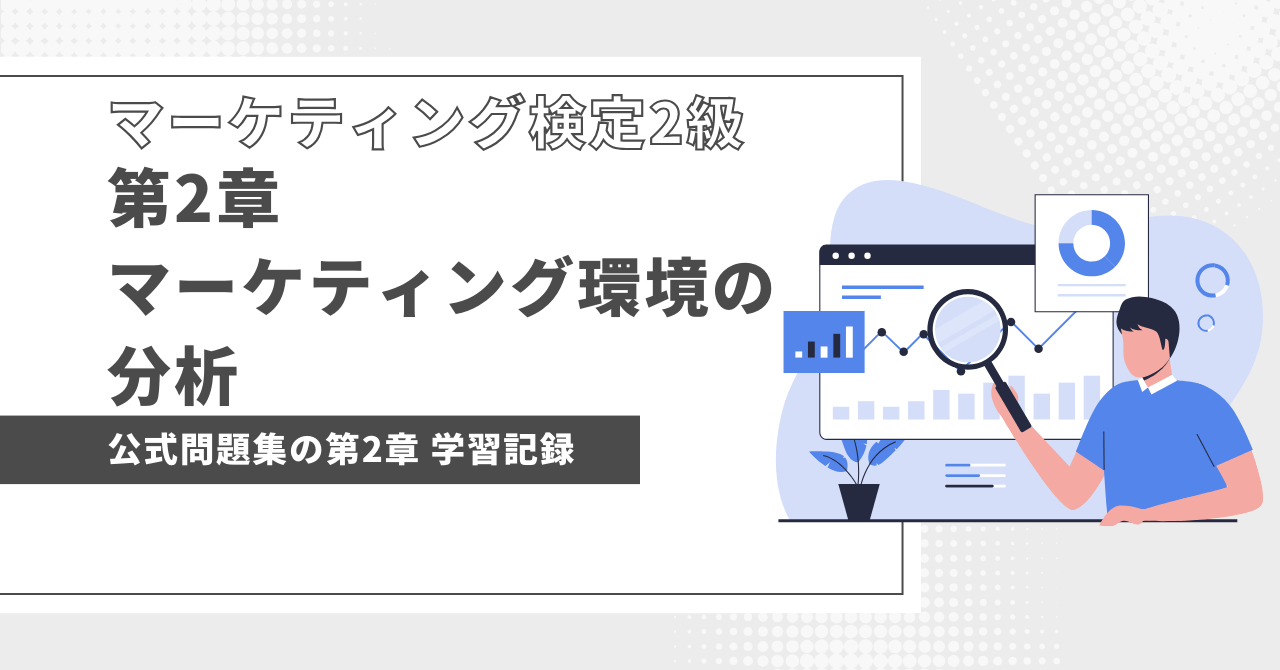
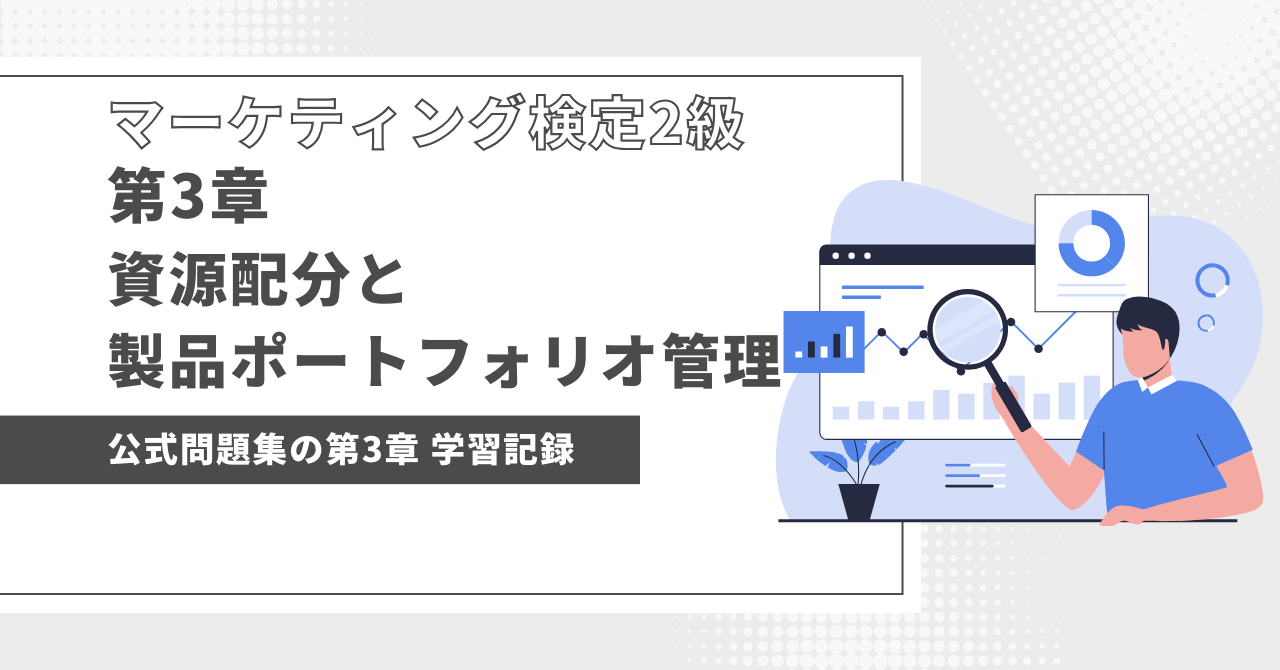
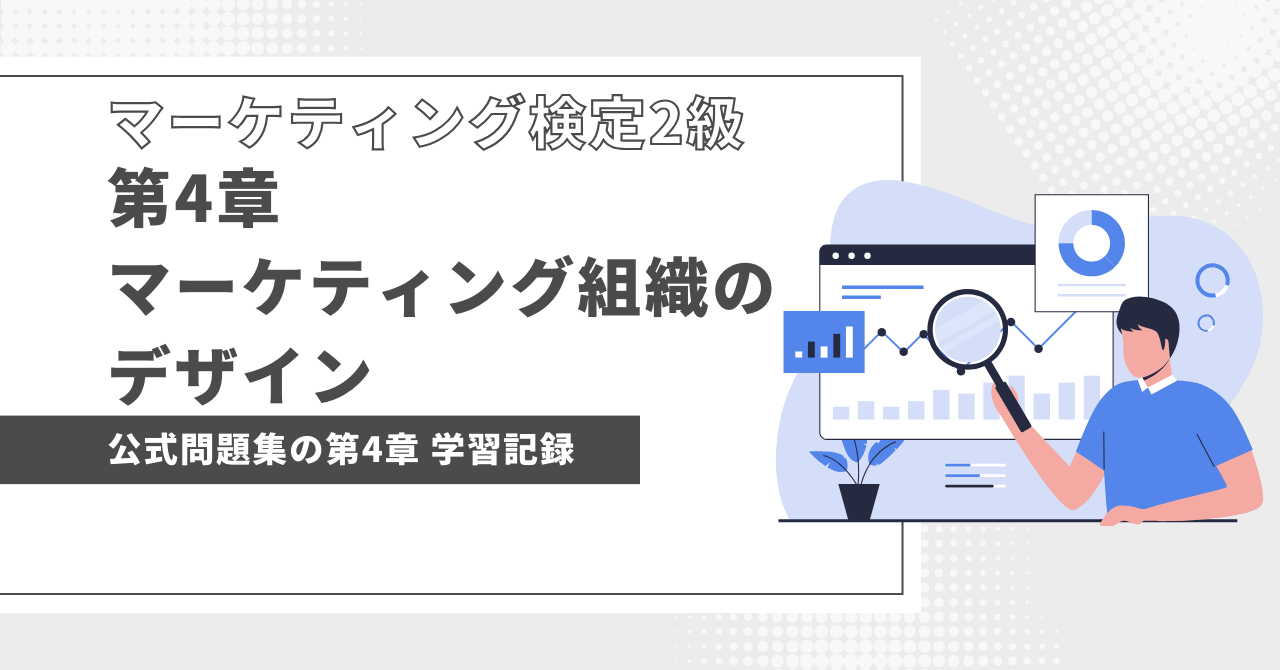
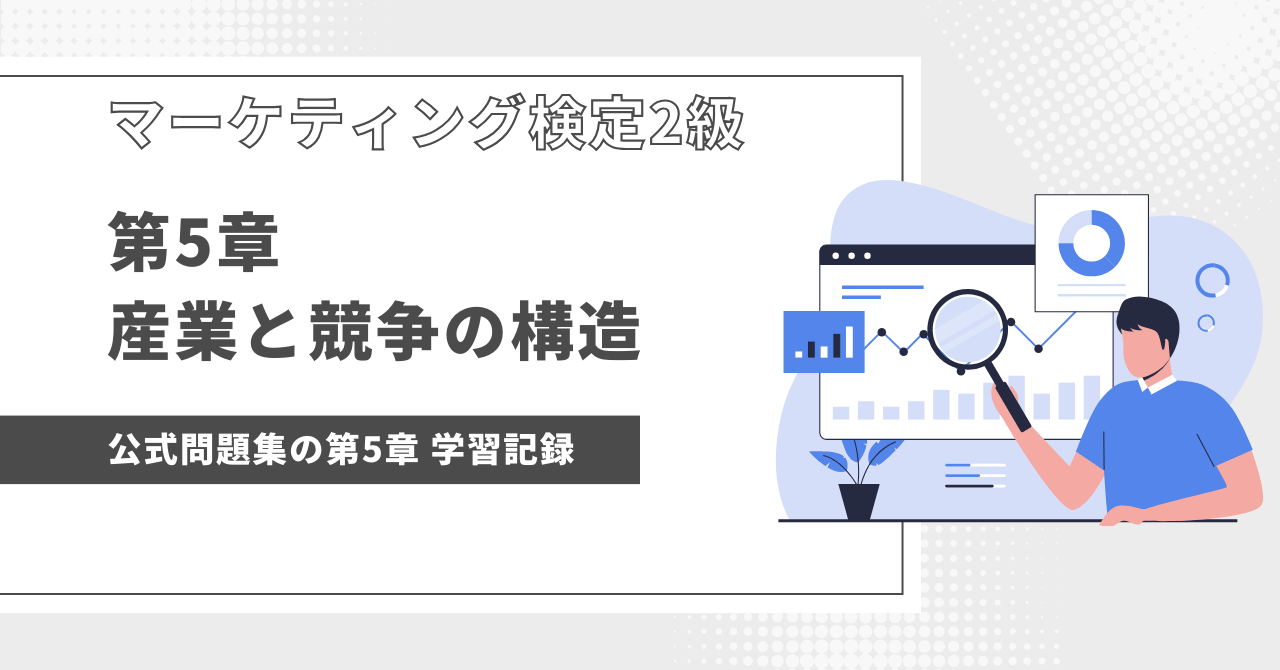
コンサル転職・自己研鑽に有効な資格は?
筆者「きつね」が実際に合格/勉強して、コンサルティング業務や自己研鑽に役立ったと思える資格を紹介します。
ぜひ、あなたのコンサル転職・自己研鑽の参考としてください!
コンサル転職前のオススメ資格/勉強記事
>>20代コンサルにおすすめ!年収を上げるIT資格【応用情報技術者試験】
>>【基本情報技術者試験】20代のコンサル転職で年収を上げるIT資格
>>【対策本あり】文系こそ取得すべき国家資格『ITパスポート』取得メリットを紹介
>>文系のIT未経験コンサルタントがプログラミングを学ぶべき3つの理由
>>【本も紹介】図解思考の技術・モデリング技術で概念を具体化【資格のUMTPもオススメ】
>>【合格体験談】マーケティング検定3級の体感難易度は簡単!勉強時間に参考書も紹介
>>【コンサル転職体験談】資格挑戦:マーケティング検定2級に挑戦|いきなり合格は無理?難易度は3級より確実に高い!
>>TOEIC400点台から800点台!コンサル実践の英語勉強法
>>【PMBOK】5つのプロセスと10の知識エリアはコンサル必修科目
>>新人コンサルにおすすめの資格「ビジネス会計検定3級」:簿記との違い・難易度・合格率をまとめた!
>>【オススメ】動画学習サービスSchoo(スクー)は評判がいい!
>>【無料あり】マーケティングが学べるオススメ動画学習サービス5選
コンサル転職に有利な資格合格に向けて
コンサル転職・転職後の自己研鑽として、資格取得を目指して勉強することはオススメです。
コンサルティング業界で働いていると、常に試験勉強をするように新しい知識をキャッチアップしないといけないので「勉強慣れ」をしておくとよいでしょう。
【STUDYing】中小企業診断士・応用情報技術者などをカバー
上記の資格をフルサポートしているわけではありませんが、スキマ時間で効率的に中小企業診断士などの資格合格を目指すなら、STUDYingも使うのがオススメです。
STUDYing中小企業診断士講座の2022年2次試験の最終合格実績が「業界No.1」
- 【合格実績 No.1!】
- ※1 2022年2次試験合格者数:167名
- 【合格者続々輩出中!】
- 2023年1次試験合格者数:510名
※1:同種の資格講座を提供している業者について、KIYOラーニング株式会社が2023年11月6日時点でHP上に記載されている合格者実績を調査した範囲での比較となります。
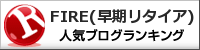
コメント